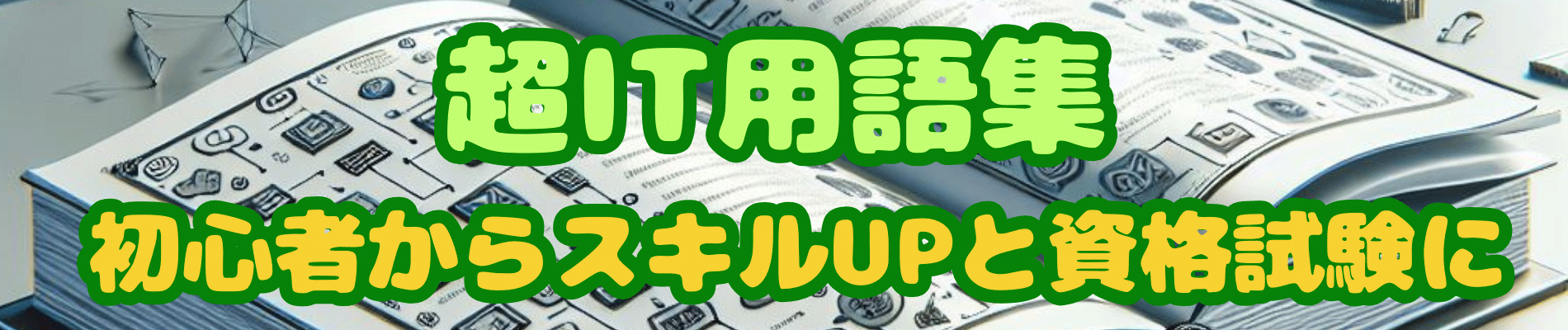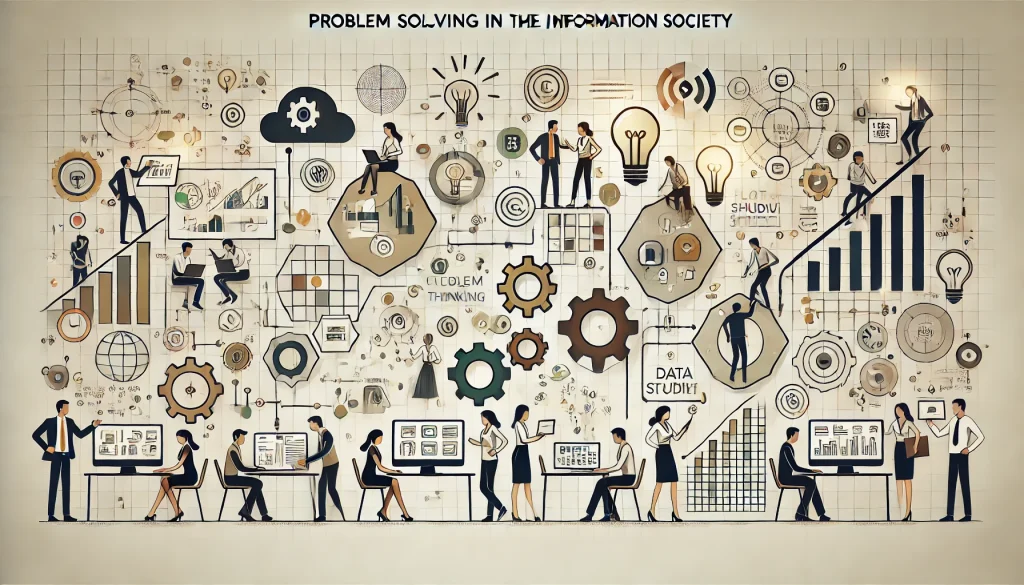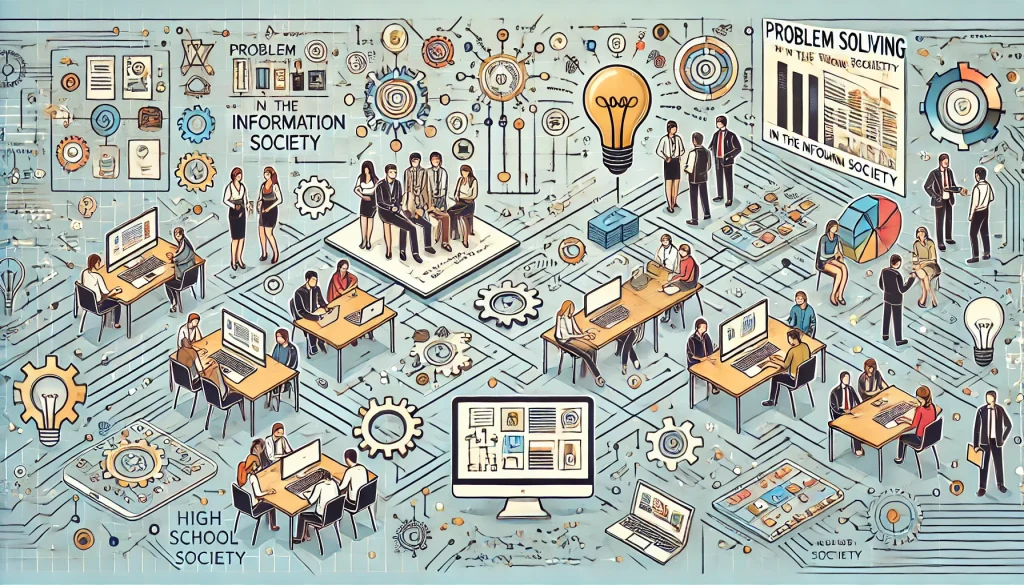情報リテラシーや二要素認証など共通テスト対策の情報I用語
「情報社会の問題解決」分野の頻出用語を網羅しました。このページに含まれる単語は以下の通り。
肖像権,情報システム,情報セキュリティ,情報セキュリティポリシー,情報の可用性,情報の完全性,情報の機密性,情報モラル,情報リテラシー,情報公開,情報社会,信憑性,生体認証,知的財産権,著作権,著作者,著作者人格権,著作隣接権,伝播性,電子マネー,電子決済,電子署名,電子認証,同一性保持権,特許権,二要素認証,認証,秘密鍵暗号方式,不正アクセス,不正アクセス禁止法,復号,平文
情報Iの共通テストや高校の定期テスト対策に、これらの語句について分かりやすい詳しい説明を掲載しています。
| 肖像権 |
| 自分の顔や姿を勝手に使用されない権利 |
| 他人が自分の写真や映像を無断で使用・公開することを防ぐ権利です。たとえば、街中で撮影された写真が本人の同意なしに広告に使われる場合、肖像権の侵害となります。 |
| 情報システム |
| 情報を管理・利用するためのシステム |
| コンピュータやネットワークを活用して情報を効率的に管理し、利用するための仕組みです。たとえば、企業の業務管理システムや顧客データベースが情報システムの一例です。 |
| 情報セキュリティ |
| 情報を守るための技術と管理方法 |
| 情報の機密性、完全性、可用性を保護するための取り組みです。これには、データの暗号化や不正アクセス防止、バックアップの管理などが含まれます。たとえば、企業の顧客情報を守るためのセキュリティ対策が情報セキュリティです。 |
| 情報セキュリティポリシー |
| 情報を守るための組織の基本方針 |
| 企業や団体が情報セキュリティを確保するために定めたルールや指針を指します。たとえば、「パスワードを定期的に変更する」や「USBメモリの使用を制限する」などが含まれます。 |
| 情報の可用性 |
| 情報が必要なときに利用可能であること |
| 情報やシステムが必要なときにすぐ利用できる状態を指します。たとえば、サーバーのダウンを防ぎ、24時間利用可能にすることが可用性を高める対策です。 |
| 情報の完全性 |
| 情報が改ざんされていないこと |
| 情報が正確であり、不正に変更されていないことを指します。たとえば、データの送受信中に改ざんされないよう暗号化することが完全性を守る方法です。 |
| 情報の機密性 |
| 情報が許可された人だけに見られること |
| 情報へのアクセスを許可された人に限定し、秘密が守られるようにすることを指します。たとえば、パスワードで保護されたファイルが機密性を保っています。 |
| 情報モラル |
| 情報を正しく使うためのルールや考え方 |
| 社会やインターネット上で情報を適切に扱うためのルールや考え方を指します。これには、他人を傷つけない表現や個人情報の適切な管理、著作権の尊重などが含まれます。たとえば、SNSでの誹謗中傷を避けたり、無断で他人の写真を使用しないことなどが実践例です。情報モラルを守ることで、健全な社会とネット環境を維持できます。 |
| 情報リテラシー |
| 情報を正確に活用する力 |
| 情報を収集し、評価し、活用する能力を指します。特に、インターネット上で得られる膨大な情報の中から正しい情報を選び取る力が求められます。たとえば、検索エンジンを使いこなしたり、信頼性のあるサイトを見分けたりするスキルが情報リテラシーの一部です。 |
| 情報公開 |
| 行政や企業が情報を公開する仕組み |
| 行政機関や企業が、一般市民や利用者に対して、透明性のある情報を提供することを指します。これにより、社会全体の信頼性向上や意思決定のサポートにつながります。たとえば、自治体が予算や決算報告を公開することが情報公開の例です。 |
| 情報社会 |
| 情報が重要な役割を持つ社会 |
| 情報が生産、消費、交流の中心となり、経済や文化に大きな影響を与える社会のことです。たとえば、インターネットやスマートフォンが普及した現代が情報社会です。 |
| 信憑性 |
| 情報が正確で信頼できること |
| 提供される情報が正確であり、利用者が信頼できる状態を指します。たとえば、公式なニュースサイトが発信する情報は信憑性が高いとされます。 |
| 生体認証 |
| 指紋認証、顔認証など:身体の特徴を利用した認証方法 |
| 指紋や顔、虹彩など、個人の身体的特徴を利用して本人確認を行う方法です。パスワードと異なり、盗まれるリスクが低いのが特徴です。たとえば、スマホのロック解除に指紋認証を使用するケースが一般的です。 |
| 知的財産権 |
| アイデアや創作物を守るための権利 |
| 発明やデザイン、著作物など、人の知的な創造活動で生まれた成果を保護する権利です。主に著作権、特許権、商標権などが含まれます。これにより、他人が勝手にアイデアを利用したり利益を得たりすることを防ぎます。たとえば、小説や音楽を無断で複製・販売する行為は知的財産権の侵害です。 |
| 著作権 |
| 創作物を守るための法律 |
| 小説、音楽、映画、イラストなどの創作物を保護するための法律です。著作権により、著作者は自分の作品をコピーされたり改変されたりすることから守られます。また、許可なく商業利用されることを防ぎます。たとえば、ネットで公開されたイラストを無断で商用利用する行為は著作権違反にあたります。 |
| 著作者 |
| 著作物を創作した人 |
| 小説、音楽、イラストなどの著作物を作成した人を指します。著作者には著作権が与えられ、無断で利用されることを防ぐ権利があります。たとえば、小説家や作曲家が著作者に該当します。 |
| 著作者人格権 |
| 著作者の人格を守るための権利 |
| 著作者の名誉や人格を守るために与えられる権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれます。たとえば、自身の名前を著作物に記載する権利が氏名表示権です。 |
| 著作隣接権 |
| 著作物を伝達する人々を守る権利 |
| 著作物を利用する実演家、放送事業者、レコード製作者などに与えられる権利です。たとえば、音楽の演奏者がその演奏を録音・配信される際に保護される権利が著作隣接権です。 |
| 伝播性 |
| 情報が瞬時に広がる性質 |
| インターネットやSNS上で、情報が短時間で広範囲に拡散される性質を指します。たとえば、ツイートがリツイートされ続けて数時間で多くの人に共有されることが伝播性の例です。 |
| 電子マネー |
| 事前にチャージして使うデジタル通貨 |
| カードやアプリにお金をチャージして利用する支払い手段です。たとえば、SuicaやPayPayなどが電子マネーの一例です。現金を持たずに素早く支払いができます。 |
| 電子決済 |
| 電子的な方法で行う支払い手段 |
| 現金ではなく、カードやスマートフォンなどを使ってオンラインまたは店舗で支払いを行う方法です。たとえば、クレジットカード決済やQRコード決済が電子決済に含まれます。 |
| 電子署名 |
| データの正当性と改ざん防止を保証する仕組み |
| デジタル文書に署名者の正当性を保証し、改ざんされていないことを証明する技術です。たとえば、契約書に電子署名を使用することで、紙の署名と同じ効力を持たせることができます。 |
| 電子認証 |
| データの正当性を保証する仕組み |
| データや通信が正当なものであることを確認する仕組みです。電子署名やディジタル証明書を用いて、本人確認や改ざん防止を行います。たとえば、SSL証明書を使ったウェブサイト認証が電子認証の一例です。 |
| 同一性保持権 |
| 著作物の改変を防ぐ権利 |
| 著作者が、自身の著作物を無断で改変されないようにする権利です。たとえば、絵画や文章を許可なく加工・編集されることを防ぐ権利が同一性保持権です。 |
| 特許権 |
| 発明を保護するための権利 |
| 新しい発明に対して与えられる独占的な権利で、他人が無断で利用することを防ぎます。たとえば、新しい製品や技術を開発した企業が特許を取得することで、その発明を守ります。 |
| 二要素認証 |
| 2FA:2種類の認証を組み合わせる仕組み |
| パスワードに加えて、別の方法(SMSコードや認証アプリなど)で本人確認を行う認証方法です。これにより、安全性が大幅に向上します。たとえば、銀行アプリでパスワード入力後にスマホへ送信されたコードを入力するのが二要素認証です。 |
| 認証 |
| ユーザーやシステムの正当性を確認する仕組み |
| アクセスを許可する前に、利用者が正当であることを確認するプロセスです。パスワードや生体認証(指紋、顔認証)などが含まれます。たとえば、スマホのロック解除に使用される指紋認証が認証の一例です。 |
| 秘密鍵暗号方式 |
| 1つの鍵を共有する暗号化の仕組み |
| 暗号化と復号化に同じ鍵を使用する方式です。鍵を事前に共有する必要がありますが、処理が高速です。たとえば、ファイルの圧縮ツールでパスワード保護を設定する際に利用されます。 |
| 不正アクセス |
| 許可なくシステムやデータに侵入する行為 |
| 権限のないユーザーが、システムやデータにアクセスして情報を盗んだり、操作を行ったりする行為です。たとえば、他人のパスワードを使ってメールアカウントに侵入することが不正アクセスです。 |
| 不正アクセス禁止法 |
| 不正なアクセスを防ぐための法律 |
| 他人のIDやパスワードを利用して許可なくシステムにアクセスする行為を禁止する法律です。たとえば、他人のメールアカウントに不正ログインする行為はこの法律で罰せられます。 |
| 復号 |
| 暗号化されたデータを元に戻す操作 |
| 暗号化されたデータを元の平文に戻すプロセスです。たとえば、暗号化されたメールを復号して元の内容を表示することが該当します。 |
| 平文 |
| 暗号化されていない元のデータ |
| 暗号化される前の、誰でも読める形式のデータを指します。たとえば、メールの本文がそのまま送信される場合、それは平文です。 |